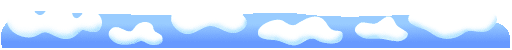
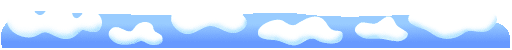

どのくらい時間がたったであろうか、気がついたらT山赤十字病院の集中治療室のベッドの上だった。ベッドの周りには桃子とその両親が立っていた。
その夜 賢介は目をさました。
「賢ちゃん、気がついた?」桃子たちが賢介に言葉をかけた。
賢介は何がどうなったのか理解できなかった、しかし頭にうかんだのは助手席に乗せていた愛犬のポチのことだった。賢介は体全体が痛くて動かすことができなかった。
「ポチは? ポチはどこにいる?」そう尋ねるのがやっとだった。
「ポチは大丈夫よ、ちゃんと家で待っているから。」 桃子の母親が答え、救急隊員から聞いた話も伝えた。
「ポチは本当に元気?」賢介は不思議にも自分の体のことよりポチの方が心配でならなかった。
一方桃子は「全く賢介さんたら、わたしたちが心配で夜も寝ないでずっと看病してあげたのに、目が覚めたらいきなりポチのことにしか聞かないなんて。」とぶつぶつ言っている。しかし、桃子の心は安堵でいっぱいになった。
しばらくして、救急の医師が回診にきて病状を説明してくれた。「頭部に外傷はあるものの奇跡的に脳には異常がありません、脳震盪でしょうね、しかし全身を強く打っているため念のため1週間ぐらいは入院が必要でしょう。」そう言った。
「1週間か、そんなに入院していなければならないのか」賢介はぼんやりとした頭でいろいろなことを考え始めた。(また、みんなに迷惑をかけてしまうな)
しかし、どうしてもポチのことが心配でたまらなくなり、桃子に「ポチは本当に大丈夫だった? どうしてもポチの顔が見たい、ここに連れてきて・・・」そう言った。
「だって、ここは病院なのよ犬なんか連れてこれるわけがないじゃないの。」
そう言われても賢介はどうしてもポチにあいたかったのだ。
そんなことを知ってか、桃子の両親は気を遣って、翌日こっそりと病院までポチを連れてきてしまったのだ。
病院の駐車場に着き車のドアを開けるとポチはまっしぐらに賢介の入院している病室を目指して走り始めた。驚いたのは周りにいる人たち、病院職員たちであった。
ポチは誰に教えられたわけでもなく賢介の病室がわかっているみたいで、周囲の制止も聞かずまっしぐらに飛び込んでいった。
ポチは賢介のベッドに飛び乗り、全身で喜びを表現しながら賢介の顔をなめ回した。
「ポッちゃん、会いたかったよ」そう叫びながら賢介もポチをなで回した。
ポチの目を見ると。なんと涙でぬれているようにもみえた。
賢介はポチにあったとたんすっかり元気になってしまった。
ポチは、桃子たちに連れ去られ、賢介は総婦長をはじめとする病院職員に大目玉をくらい強制退院させられるはめになったのである。